日本ではいつから木の下で花見を楽しむようになったのか?花見文化の歴史について
お花見は日本人特有の風習として海外でもよく話題に上がります。
確かに、その時期になるとお弁当を持って桜をみにいく、その風習にも
歴史があったはずですよね。
日本人はいつから、なぜお花見をするようになったのでしょうか
お花見の始まりは奈良時代からとされています。
奈良時代には花見はまだ庶民にはひろがっておらず貴族たちが花を見て
歌を詠む会、的なものでした。
しかも桜ではなく梅を見て楽しむ、といったものが花見とされていました。
平安時代にもまだ花見は一般化されていませんでした。
平安時代の当時の書物「古今和歌集」の歌の数を見てもわかるくらい桜を詠んだ歌が増えてきます。
梅よりも圧倒的な人気が出てきました。
鎌倉時代になるとようやく武士や町民たちの間にも浸透して行きました。
貴族時代が終わり武士が支配するようになり各地に広まっていったとされています。
そしてついに江戸時代になると庶民にも花見が浸透しました。
これは有名な八代将軍、徳川吉宗(徳川吉宗)が行った享保の改革の一つです。
隅田川の川沿いにみんなが好きな桜を植えることにより、大勢の人がその場所に
集まり土が踏み固まります。そうすることで川の氾濫を避けれます。
また桜のような広葉樹は根がよく張るので水害対策というわけです。
よく考えられてますね〜。感心します。
現在の隅田川の桜をそういう視点から見たくなりますね。
そこに咲いている桜は江戸時代から時代が変化していく様子を知ってるんですよね。
神秘的。
そして今、庶民の私が花見をして楽しめるのは徳川吉宗さんのおかげですね。
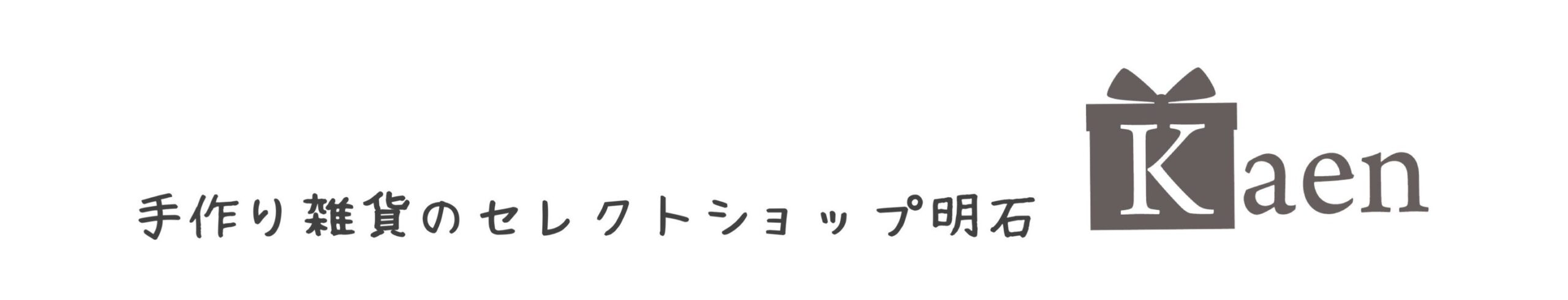











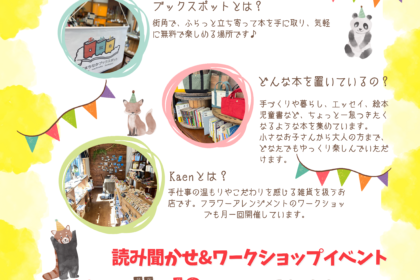


コメントを残す